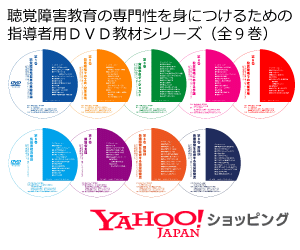軽・中度難聴のむずかしさ

聞こえにくい子どもを育てた親として
大塚ろう学校専門家研修
AHさん(保護者)
<はじめに>
高校生の聴覚障害の息子がいます。まったく聞こえないのではなく、補聴器をつけた聞こえにくい子どもとしてどのような子育てをしてきたか、またその過程でどのようなことを考えたか、今日はお話させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
軽・中度難聴のむずかしさというのは、いくつかの問題があると思いますが、まずはある程度聞こえているがために、障害の発見が遅くなり、言語獲得の面で学齢期に大きな問題を抱えたままで教育を受けているケースが多いということがあります。障害の発見時期の問題が以前からあった大きな問題ですが、今は、また別な問題が起きています。新生児聴覚スクリーニングの検査によって、軽度難聴や片耳難聴などの発見が新生児期に行われるようになってきたということです。いままで発見が遅れていたのが、早くなったのだからいいのではないの、と思われるかもしれませんが、なかなかそうはいかず、そのような軽度のお子さんや片耳難聴のお子さんに、最早期からどのような支援、療育をしていけばいいのか、なにもわかっておりません。基本的には、そうしたお子さんへの受け皿は現在ほとんどどこにもありません。また、70dB未満の聴力では、福祉の対象にもなりません。まだ若いご夫婦が、生まれたばかりのお子さんに中度の難聴が発見され、補聴器が有効だと言われ、それを自費で購入しなければならないということが起こってきます。私の地元の稲城市にもそうした親御さんがいて、なんとかならないかと相談されていますが、行政に要望を出しても、国の決まりどおりという返事しか返ってきません。子育て支援の一環として何とかならないかと思っています。厚生労働省のほうでは、眼鏡と同じで、視覚障害のお子さんは福祉の対象になるが、ただの近視では眼鏡は自費だからという考えらしいのですが、ちょっと違うのではないかと私は思っています。新生児スクリーニングで早く発見されても、その療育の受け皿や福祉的支えがないという問題があるわけです。
さらに、最近は、高度難聴やろうだったお子さんが人工内耳の手術を受け、聴覚活用ができるようになり、教育の場をろう学校ではなく、地域の小学校を選んで進学されるケースが増えてきつつあります。そうしたお子さんは、中等度難聴の子どもに近しい聞こえ方になるらしく、インテグレーションでの中等度の子が抱える問題が同じようにそうしたお子さんにも起こりうることが予想できます。中等度難聴の子どもたちが、地域の小・中学校でどのような困難を抱え、それはその子たちの人間形成にどのような影響があったのか、このことを医療側も保護者も教育界も、真剣に考えてほしいと願っています。こうした専門家研修会の中に、軽・中度難聴の問題を取り上げ、企画してくださった大塚ろう学校に感謝しております。また、本日この場においでくださり、私の話を聞いてくださる皆さまにも、心からお礼申し上げます。限られた時間ですが、親から見た軽・中度難聴の難しさを話させていただきます。
<子育ての過程で見えてきたもの>
今日、お話しする内容は、次の五つの項目について触れたいと思います。
◎ “聞こえにくさ”を聞こえる人間が想像するむずかしさ
◎ 教育環境選択の困難さ
◎ 親の思いと本人の思いのずれ――情報保障の問題
◎ 手話との出会い、仲間との出会い――自分の居場所探し
◎ 肯定的自己像の獲得のために必要なもの
最初の“聞こえにくさ”を聞こえる人間が想像するむずかしさについては、私の話の最後にまとめてお話したいと思います。息子を育てて、そろそろ18年になろうとしていますが、本当に息子の聞こえにくさを聞こえる親が想像する、しかも学校生活の場面を想像することはむずかしく、いまだに、あーそうだったのか、こういうことだったのかと反省させられることの連続です。また、聞こえにくさとは別に、不快な音に対しての感じ方も、私たち聞こえる人間とは違い、息子は、幼児期には、地下鉄の丸の内線の音が大嫌いで、恐怖を感じて泣いてしまうほどでした。先日、ある成人の難聴の方のお話では、食器の触れ合う音が嫌いで、ご夫婦での家事の分担で皿洗いだけは免除してもらいたいというお話を聞き、聞こえる人間の感じる不快感とは、きっと桁がちがうのだろうなと改めて思いました。そうしたことを言葉で説明できるようになるまで、子どもは年数がかかりますので、幼児期はずいぶんいろいろな思いをしながら、集団生活を送ってきたのだろうと思います。聞こえにくさを聞こえる人間が想像することは、むずかしいものだとしみじみ思っています。
では、わが子の育ちをご紹介しながら、今あげております項目に触れていきたいと思います。
<わが子の育ちについて>
息子は、昭和61年9月生まれの第2子です。4歳上に長女がいます。息子の場合は、中等度の難聴だったのですが、発見は早く、新生児期にABR検査で聴覚障害の疑いありと告げられました。いくつかの合併症のある子でしたので、出産病院で、いろいろな検査をして、聴覚でひっかかったというわけです。生後1カ月、3カ月、半年とABR検査をして、その後、小児難聴の専門の病院を紹介され、7カ月で聴覚障害の確定診断が出ました。8カ月から1歳までT大学病院でホームトレーニングを受けました。
1歳1カ月で補聴器を右耳のみ装用(右耳65dB、左耳110dB)。身体障害者手帳6級ということで、福祉の補助は受けられました。
<育児の過程で与えられた言葉>
育児の過程で、いろいろな方から与えられた言葉があります。たくさんの言葉をかけていただいたのでしょうが、強く残っている言葉をいくつか上げます。
3カ月健診のときに、どうも聴覚に障害があるらしく、経過をおって検査しているとお話したら、保健所の小児科医から「お母さん、難聴は教育、訓練ですよ」ということを言われました。
また当時、私は難聴児の子育てがとても心配で不安で、家にいても落ち着かず、手に入りそうな書籍を買ったり図書館で借りて読んだりして、どうしたらいいのか悩んでばかりいました。そうした本の1冊に全国難聴児を持つ親の会の連絡先が載っていました。勇気を奮って、その連絡先に電話をして、親の会の先輩の方に1時間くらい泣きながらお話し、いろいろアドバイスもいただきました。その方からは「1日24時間を神様に倍にしてもらっても難聴児の親には時間が足りないくらい子どものためにやることがたくさんある。でも、親がちゃんと教育すれば必ず成長する。私の子も今は大学院で研究している。でも言葉を育てることはできても、心を育てることはなかなかむずかしい」という内容のことを言われました。1日48時間あっても足りないほど、難聴児の親はやることがあるのか、しかし、親が一生懸命やれば、大学院にまで進めるようになるのかとそのときに思いました。
ホームトレーニングを受けた大学病院の耳鼻科医からは、「補聴器をつけて訓練すればことばは獲得できます。手話でなくても大丈夫。ろう学校に行かないでもやっていかれます」と診断のときに言われ、また難聴の説明のときに「子どもを育てるのは専門家ではない、他の誰でもない、親であるあなた方なのですよ」ということを強調されました。
こうして0歳児のときに与えられたいくつかのことばは、私の子育ての基礎となり、方向性を決める上での大きな影響となりました。
<どのような療育を受けたか>
不安で落ち込んでばかりいた私も、だんだんになにかやらねばならない、聴覚障害児には訓練が必要、親が時間をかけて懸命に取り組む必要がある訓練があるらしい。しかしどこでそれを教えてもらえばいいの?何をしたらいいの?と確定診断後の療育に気持ちが向くようになりました。ホームトレーニング終了後、大学病院からは聴力は軽い方なので補聴器をつけて家庭で丁寧に接すればいいとのことで、その後の療育先は紹介されませんでした。3カ月ごとに受診し、聴力検査や補聴器の調整などのケアを受けるだけの日が続きました。しかし、障害のある子をどう育てていったらいいのか、どう接したらいいのか、聞こえにくさをどう補ったらいいのか、自信がなく、だれかに助けてもらいたいという思いが強く、たまたま知り合いのお母さんから教えられ、地域の障害児が通う通所訓練施設に相談に行きました。運動発達も遅れていた息子は、1歳半からそこの通所訓練に週2~3日通うこととなり、そこでいろいろな障害のある子を育てているお母さん方と知り合い、動物園の遠足や夏の海での宿泊行事などに参加して、子どもと楽しく遊ぶ体験をたくさんさせていただきました。手遊び歌なども私はなにも知らなかったのに、その施設でずいぶんいろいろ教えていただき、子どもと一緒に遊ぶ楽しさを味わえるようになりました。ただ、そこではダウン症のお子さん、発達障害のお子さん、肢体不自由のお子さんたちが多く、聴覚障害の子は息子以外だれもいなくて、聴覚に関する専門的な指導は受けられませんでした。
子ども同士からのもっと豊かな刺激がほしいと思い、2歳半から保育園に週3回母子通園させていただけることとなり、そこで同年齢の聞こえる子の成長ぶりにびっくりしてしまいます。わが子にもっとなにかしてやりたい。このままではいけないとあせりもしました。聞こえる子たちとわが子を比較して、その大きな落差のある現実を突きつけられてどうしたらいいのだろうと悩みも深くなりました。そうしたときに、大学病院の言語指導のグループに入れていただけることとなりました。3歳過ぎのことです。週2回、大学病院に通い、個人とグループの指導を受け、週3日は保育園に通うということを小学校の入学まで続けました。そして、大学病院の指導を受け始め、息子は音声語をどんどん砂に水が吸い込むように吸収し、身につけていきました。それは、やはり中等度の聴力だったということが大きな味方になったのだと思います。
<当時の指導法は聴覚口話法のみ>
当時は、指導のやり方は聴覚口話法のみで、口形をはっきりさせ、よく子どもに見せて明瞭に話す。少しオーバーぎみに表情や動作をつけ、子どもを注目させる。子どもの興味をひく題材を探し、何度も繰り返し楽しく遊ぶ、絵日記や再現遊び、ごっこ遊びを家庭で工夫し、言葉かけをしていく。そうしたことは、大学病院でSTの先生のやり方を見、基本を学んで、家でその子に合わせて母親が考えて作り上げていくというやり方でした。
生活の場がすべて言語訓練の場となり、このことを覚えてもらうためにどのような生活をして、どのような場面を設定してと、いつも考えていました。息子の場合は、手話、指文字、キュードなど何も使わずに、指導を受けました。文字は早めに覚えるように工夫し、4歳過ぎには読めるようになり、5歳前にひらがなも書けるようになりました。日記指導を5歳くらいから始めて、並行して子供向けの親の日記も書き、それを使って読み取りの力を育てていきました。しかし、息子の場合は途中からパターン日記になってしまい、いまだに文章を書くのは大嫌いです。親のやり方に少々無理があったのかなと反省しています。絵本は山のように読んだという言葉どおり、十分に活用しました。本好きの子には育ちました。
<インテグレーションをめざして>
このように大学病院で指導を受けるということは、就学までに言語力を育て、当然のように地域の小学校にインテグレーションをしていく、そのために親子で頑張るということでした。小学校入学後にスムーズに聞こえる集団に入れるようにさまざまな集団の行事やルールを身につけておき、勉強面のみではなく、あらゆる面で先取り教育をしていきました。幼稚園などの行事理解の徹底や前もっての練習により、聞こえる子たちの集団にすでに知っていることとして安心して参加できるようにする、そのような幼児期を送っていたと思います。十分な言語力と就学前までに小学2年生くらいまでの学習を終え、その貯金をもって地域の小学校に入学していく、まさにインテグレーションをめざして、まっすぐな一本の道を歩んでいたようでした。
<幼児期から小学校低学年までの息子の言葉から その1>
さて、そのような日々の中で、本人はどのような思いをしていたのでしょうか。大学病院と平行して通っていた保育園であった出来事をめぐっての、息子の言葉を紹介します。
週に3日通っていた保育園で友達とアニメのキャラクターになるごっこ遊びをしたときに「僕は○○ちゃんと2人で遊んでいるとわかるのだけど、他の子が入って3人、4人になると、だれが何をやっているのか分からなくなるんだ。だから、他の子が入ると僕はぬけちゃうんだ。」-保育園の先生から「自分のやりたい遊びしかやらない協調性のない子」という指摘を受け、家に帰ってから、今日はお友達と遊んでいるときに途中でやめて、1人でイスにすわっていたんだってと聞いたときに答えた内容です。幼児ですので、このとおりの言葉ではありませんが、65dBでも多人数のなかでのコミュニケーションは困難だということにすでに気づいていました。本人なりの自己防衛であり、聞こえにくさの自覚だったと思います。
<幼児期から小学校低学年までの息子の言葉から その2>
就学児健診や教育委員会とのやり取りを経て、地域小学校に入学が決まり、上の娘と同じ小学校に入学する朝のことです。
小学校入学式に出席するため、両親との登校時、もうすぐ校門が見えるというところまで来たときに、急に立ち止まり、後ずさりしながら 「僕、小学生になる気持ちじゃないよ。赤ちゃんに戻りたくなっちゃった。」 親である私も大きな不安、ちゃんとやっていけるのだろうかと心配しながらの就学だったのですが、本人はもっともっと不安だったのでしょう。入学式では、補聴器を手で隠しながら入場してきました。
そうして心配しながら始まった小学生生活ですが、担任の先生や学校側の配慮をいただき、楽しい学校生活を過ごし始めました。少し慣れ始めたころの言葉です。
「学校っておもしろいね。先生が<おかし>って言うんだよ。押さない、駆けない、しゃべらない、なんだって。先生っておもしろいことを言うね。」座席の配慮などがあれば、中等度の子は担任の先生のゆっくりはっきり話す内容は、何とか聞きとれ、つかめていました。毎日楽しく登校し、放課後も近所の子とよく遊ぶ、元気な一年生になりました。大学病院の指導は就学までで終了し、専門的な指導や聴覚管理の場がなくなったので、1年生の終わり頃より、市外の難聴学級に通うようになりました。本人にとってというより、親の心理的な支えがほしかったのだと思います。
<幼児期から小学校低学年までの息子の言葉から その3>
2年生の半ばから、授業の進度は早くなり、また教室内での子ども同士のやりとりが活発になってきました。担任の先生からも、クラスの雑談が聞き取れず、それを後から説明しても、みんなのそのときの楽しさが伝えられないで、困っているという話が出ていました。そんな頃の授業参観の日に、だれかの冗談にクラス中が笑い転げたときに
「なんで笑うんだ。僕はちっともおかしくない。何がおかしくてみんなが笑っているのか分からない。笑うな。」と言って、一番仲良しの友達の椅子をけっ飛ばすという出来事がありました。
校庭や体育館でのマイクの声などは聞き取れず、FM補聴器を試してみたり、補聴器を変えてみたりした3年生の頃、「僕一人が聞こえない子なんだよ。僕一人が補聴器をつけているんだよ。学校のみんな全員がわかっても僕一人がわからないときがあるんだよ。」と訴えてきました。親ができることは、補聴器の調整を変えてもらったり、当時故障の多かったFM補聴器を車で工場まで持ち込み、早く修理をしてもらうくらいのことしかできませんでした。
<聞こえる集団の中で>
学校中聞こえる人ばかりの中で、補聴器をつけた聞こえにくいたった一人の存在であることの自覚が、息子は強かったようです。また、放課後の遊びの中でも取り残される体験をいろいろしていたようです。かくれんぼ遊びの時に片耳しか補聴器をつけていない息子は、左右の方向がわかりません。鬼になってもなかなか見つけ出せずに、他の子はつまらなくなり、鬼を残して他の遊びを始めてしまったことがありました。
遊びの中でも取り残される、置いてきぼりにされる体験をしていましたが、親にはその寂しさは、訴えてきませんでした。
また、3,4年生のギャングエージといわれる時期の群れて遊ぶ集団には入れませんでした。家でもっぱらファミコンゲームをして遊んでいて、ファミコンとおやつ目当ての子たちが遊びに来てくれました。しかし、ゲームをしながらの会話には入れず。聞こえる子たちが駆使する音声言語の複雑さには太刀打ちできなくなりました。イントネーションやアクセント、声の調子などにこめる微妙なニュアンスは息子にはわかりませんでした。
<場の雰囲気をつかめない子、全体の気持ちに乗れない子、わがままな子、自己中心的な子、みんなより幼い子>という扱いになり、お世話される子という自分の立ち位置に本人は甘んじられず悔しい思いをしていたようです。そして勉強だけでは負けない、ばかにされたくないという強い思いや自負心が出てきて、聞こえる集団は安心できる仲間集団ではなくなっていきました。
<インテグレーション環境の中で>
小学校の高学年になると、聞こえる子どもの精神的な成長にどんどんついて行けなくなりました。集団の中での調整能力や協調性、皆と一緒になにかを成し遂げる喜び、達成感などから置いてきぼりになっていきます。学校生活の中では勉強よりもこうした力をつけていくことが大事なのではないかと思います。勉強はある意味、一人でもできる。一人ではできないものはなにか、集団生活の中で本当に育てなければならないものはなにかを、親はもっとよく考えるべきだったと思っています。たとえば、学芸会の準備で長い時間かかって皆疲れきっているとき。でもそうしたときに「あと少しだからみんな頑張ろう」とだれかが一言声を出す。疲れていたのは自分一人ではないのだ。他の子も疲れていても最後まで頑張ろうとしているのだとその声かけでわかる。そこでまたみんな疲れがとれてあと一頑張りできる。そうした言葉のご褒美に聞こえない子、聞こえにくい子はあやかれないのではないかと思います。
また、大人が教えられることと教えられないことがあります。簡単に言うと悪知恵がつかない。正論しか言えないということでしょうか。「本音と建前」の建前の部分でしか物事を捉えられない傾向があります。親や教師は正しいことしか言えない。裏の部分、陰の部分、隠している部分が聴覚障害の子にはわからない。インテグレーション環境では人を表面的にしか理解できなかったり、本音でぶつかる相手がいないという状態が多いのではないかと思います。
そうした人間心理の本音や複雑さ、心の中のどろどろしたものなどは、息子は中学1年生のときの長期のイジメ体験の中で学んだのだと思います。悲しい体験だったのですが、中学校生活がなんとか落ち着いてきたときに、こんなことを言っていました。「人間の心の複雑さを学んだよ。お母さんに聞いても、答えてくれるのは正しいことばかり。でも人間ってそうじゃないんだよね。」
純粋培養してしまった、大人から見ていい子は、子ども集団の中では「変なやつ」と思われてしまうことがあるのだと、また親としての至らなさを思い知らされました。
子どもにつけてやりたい力は何なのか?どんな大人になってほしいのか?どんな人間となり、どのように社会に出て行ってほしいのか?目先のことではなく、10年後20年後を考えて、真の子どもの成長を支える道はなにかを考えるべきだったと思います。私の子育てのころは、迷わずインテグレーションを選び、その環境の中でいかにうまくやっていけるかを考えていましたが、インテグレーション環境の中で、本当に社会性はつくのでしょうか?多くの子どもたちがいることだけで豊かな環境だと言えるのでしょうか?このことは、聴覚口話法の検証とともに多くの方に考えていただきたい問題です。
<教育環境の選択>
今、お話したようにインテグレーションは、聴力の重い子のみならず、軽中度の子にもある意味、負担の多い環境であるということは、お分かりいただけたかと思います。しかし、音声語でやり取りできる軽中度の子は、今までのろう学校は選択しにくかったのも事実です。最近、ろう学校の就学基準も見直され、また特別支援教育へと障害児教育が転換されます。なにがなんでもインテグレーションという切羽詰まった選択ではなく、柔軟ないつでもその選択を見直しできるような教育になっていってほしいです。
それから、軽・中度の子どもたちは、本来なら難聴学級が支えになってくれるはずですが、私の地域には難聴学級はなく、市外への通級は時間的にも体力的にも負担が大きかったです。また一番大事な在籍学校への難聴理解啓発などはなかなか行えず、親だけでは学校への働きかけが大変でした。現実には難聴学級が軽中度の子の十分な支えにはなっていないと言えます。親たちにしたら、どこにも理想的な教育環境はないというのが、正直な思いです。わが子に少しでも教育を受けやすくしてやりたいと親たちの個別な試行錯誤が、今いろいろ行われています。-愛媛県松山市の学校生活支援員制度、世田谷区の駒沢中学でのパソコン要約筆記による情報保障の試み、川崎市の小学校での手話での授業保障など、待っていられない親たちがいろいろな方の協力を得ながら、教育環境を少しずつ変えていっています。
<親の思いと本人の思いのずれ -情報保障の問題->
そうした情報保障の広がりの中で、親の思いと本人の思いにずれが生じているケースがあります。
聞こえない、聞こえにくい子たちの学習を支えるために授業に情報保障をつけたい、というのが親の思いの多くだとしたら、本人が求めているのは、集団の中での一体感を抱きたいというのが多いのではないでしょうか。同じ空気を吸い、クラスメートの冗談に笑い転げるクラスの一員としての存在、そんな自分になる手助けを情報保障がしてくれたらという願いがあるように思います。
学校は子どもにとって長時間過ごす生活の場、勉強以外の学校生活がどうなのかは、とても大切なことだと思います。しかし、休み時間やお昼休みの雑談になかなか情報保障はつけられません。
→今は、手話を使い、それを同級生に教えてコミュニケーションをとる聴覚障害児が出てきました。いろいろな力を獲得し、それを発揮していける環境になりつつあるのかもしれません。多様性の時代になってきたとも言えます。
<手話との出会い、仲間との出会い -自分の居場所探し->
聴力が重いお子さんに比べ、軽中度の子は、手話との出会い方もなかなか難しいです。ある場で、他にも難聴児がそばにいたので手話つきで私が話しかけたときに、ある中等度難聴の女の子は、「私は手話でなくてもわかるからね」と言い、私が手話つきで話すのを嫌がりました。同じ補聴器を使う聴覚障害の子どもなのに、音声語が使えるということから、手話など自分には必要ないと思っている子どもがたくさんいます。しかし、そのままでは、自分以外の聴覚障害の人、手話を使う人とはコミュニケーションがとれません。たぶんそのまま、手話を必要としないで育っていく子たちもいることでしょうが、どこかで同じ障害のある人たちと出会ってほしいものだと思っています。
また、聞こえる社会だけで過ごしていて、音声語の簡便さにどっぷりとさらされている。 そして自分の言いたい事、自分の要求は音声語で通じてしまいます。聞きとれなかったことに、子ども時代はそれほど困らずに過ごしていくこともできます。自分の聞こえた範囲で判断し、それでいいと思っている・・・、そこから次の段階に行くときにとても時間がかかってしまうケースがあります。たとえば、高校まではなんとか自分のやり方で学習についていくことができても、大学では大教室でマイクを使った講義に途端に苦労する学生がいます。しかし、自分は聞こえているんだ、これまでもこれでやってきた、特別扱いをされたり、情報保障などいやだ、まして手話などとんでもないという学生がいます。そして自分の障害を認識するのに1年、2年とかかってしまうこともあります。
「自分は聞こえている」と思っている限りは聞こえない集団には入れない、では、本当に聞こえる集団の中だけでやっていけるのかというと、そこでも中途半端、その集団にも入れない。どこにいっても不全感があるという聴覚障害の青少年がいます。
聞こえる、聞こえないに関わらず、仲間、友人を強烈に求める思春期に、どのような人との出会いがあるか、自分の居場所が見つかるのか?これが、とても大きな意味を持つと思います。たった一人の聴覚障害児、そうならないようになんらかの支える場が必要です。今は、さまざまな聴覚障害関係の活動があり、アンテナをはっていれば、情報を得ることができます。フリースクールや親の会の活動、聴覚障害の大学生の団体などがありますので、そうした情報を得て、どこかで誰かと出会ってほしい、そして自分以外の人と出会うことで、自分自身をそこでまた見直してほしいなと思います。
<肯定的自己像の獲得>
聞こえる集団の中では、よくわからないままで回りに合わせて行動していたり、いつもみんなからワンテンポずれてしまう。集団での話し合いに参加ができず、結果だけを知らされ、自己表現の機会が少ない。このような状況では、当然自分に自信がもてない、自己評価が低くなりがちです。自分はこれでいいのだ、ありのままの自分でいいのだという自己肯定感は、仲間や友人、先輩との出会いの中で育まれるのではないでしょうか。他者との出会いを通して、初めて自分が置かれている状況が見えてきます。そして自分より先を歩んでいるロールモデルの存在が、聞こえる人間ではない自分の将来を考えるときに大きな励みになると思います。聞こえる集団の中のたった一人の聴覚障害児では、肯定的自己像の獲得は難しいのではないでしょうか。自分を好きになり、自分の将来になんらかの夢を持てること、これは現在では、聞こえる子どもたちにも難しい課題なのかもしれませんが、障害というより高いハードルがある子どもたちにとっては、さらに難しい問題となっています。インテグレーションの教育環境の中にいたとしても、どこかでそうしたものが用意されていることが、子どもの成長を支える大事なキーポイントになると思います。
<聞こえにくさとは?>
さて、一番最後に残した項目ですが、聞こえにくさを聞こえる人間が想像する難しさについて話したいと思います。私自身が聞こえる人間ですので、子どもが日々感じている不自由さを十分わかっているわけではありません。日常生活をともに送っている私でも、わが子の状況は、本人からの訴えがない限りわからないのです。
まるで聞こえないのではなく、聞こえにくい、聞き取りにくい――かえって聞こえていないほうが説明は簡単、周りに自分の聞こえ方を説明しにくい、また話したとしても理解されにくい、環境に左右され、同じような状況なのに聞こえたり、聞こえなかったりする、周りにとっても自分にとってもあいまいである。そして発音が明瞭だと、いくら説明しても回りはすぐに聞こえていると勘違いしてしまう。そうした中等度難聴の中学生の訴えが、大塚ろう学校の『センター通信』に紹介されています。京都の二条中学という固定性の難聴学級のある生徒が書いたものです。中等度難聴の子どもの心の動きがよく書かれていますので、ぜひ読んでください。
軽・中等度の難聴児は、生育の過程では音声語はあまり困難なく獲得できますが、それで言語獲得がすべてスムーズにいくとは限らないわけです――思考言語の獲得はおしゃべり言葉とは別の次元の問題で、ぺらぺらおしゃべりはするが、きちんとした思考言語、学習言語の獲得に結びつかない子どもたちがいます→田中美郷先生がまとめられた「中等度難聴児の言語の問題と対策-新生児聴覚スクリーニングに関連して-」(田中美郷・大串一枝、平成16年3月発行・厚生科学研究)という冊子で、そうした子どもたちの事例がいろいろ出ています。聴力が軽・中度であっても、その発見の時期、生育過程などにより、言語力の獲得が十分でなく、学校教育を受ける上で非常に困難を抱えている子どもや、また言語力は十分あるが、インテグレーションの中で、小学校中学年・高学年でコミュニケーション不全から、学校生活が辛く困難になっていった例などがいろいろあがっています。
それからしゃべり言葉と思考言語の違いについては、聞こえる子どもたちのバイリンガル教育について書かれた「英語を子どもに教えるな」(市川力、中公新書ラクレ)という本が、セミリンガルの危険性についてふれています。セミリンガルというのは、日本語も英語も中途半端な獲得しかできない状態です。アメリカで暮らす日本人の子どもたちの多くが、発音だけはネーティブ並みでも、話の中身や考える力は、中途半端にしかつかず、どちらの言語でも十分な力となっていないそうです。これと同じことが、軽・中度難聴児にも起こっています。ぺらぺらしゃべっているのに、言語力、思考力が育っていない、言葉の根っこが浅い子どもたちがいます。親や教師は話していることに安心して、言語力の大きな欠落に気づかず、学年が上がってからこれは大変だと思っても、なかなか元に戻っての言語獲得の再学習はできないというケースです。これは、これから増えてくる人工内耳のお子さんにも、同じ問題が起こりうると思っています。
軽・中度難聴児がたぶん一生を通じて抱える問題は、コミュニケーションの困難さだと思います。聞こえない、ろう者の場合、確かに聞こえる人と対したときにはコミュニケーションに困難でしょうが、手話を使うろう者同士では困らないわけです。しかし、その生活のすべてを聞こえる社会で過ごす手話を知らない難聴者は、どの場にいてもコミュニケーションの不全感からは逃れらないのではないかと思います。聞こえる集団の中での孤立感を、息子は透明なガラスのカプセルに入れられて、周りを見ている感じと言っていました。
が、成人難聴者のHPからいろいろなことを学びながら、ご自分の子育てに生かしていられます。
<聞こえにくさは厄介なもの?>
手話を知らない難聴者に情報保障をするのは難しいと思った体験があります。補聴器をつけたり、つけなかったりする程度の難聴の方でしたが、息子の難聴学級時代の同じ保護者でした。保護者会に出てくるときも、なにも情報保障をつけず、「難聴児の親同士なのだから私にわかるように話せるはず」と言われても、それはなかなか難しかったのです。ゆっくりはっきりと話すように最初は気遣っていても、10人前後の親や教師で話し合っているうちつい話に夢中になり、早口になり、横を向いてということになってしまいました。保護者会にはろうのお母さんのために手話通訳がついてきたりしていたのですが、手話はまったくわからず、覚える気持ちもない方でした。ノートテイクという制度があるので、一度つけてみたらとすすめ、その手配をしましたが、ついたノートテイクの内容に満足されないのです。全部書いてくれるわけではない、時には書き間違えることもある、聞こえている声とずれて書かれるとかえってわかりにくい、ノートテイクは私には必要ないと言われてしまいました。ある程度聞こえる方には、手書きの文字情報には限界があるなと思いました。パソコン要約筆記なら、話し言葉の約6,7割を文字化することができます。それでも、話される言葉の全部ではないし、また文字での情報伝達では、伝わりにくいニュアンスや感情もあります。手話もノートテイクもパソコン要約筆記も、いろいろなツールを場に応じて使いこなせる難聴者になったほうが便利かなと思っています。
難聴者の方が言われた言葉や、難聴者について言われていることで印象的な言葉がいくつかあります。ある難聴者ファミリーの父親が、自分の子どもに話した言葉ですが、「全部わかろうとしなくていい、いい加減でいいんだ。すべてわかろうとすると疲れるばかりだ」と教えたそうです。 「まあ、いいか」「わかったふり、聞こえたふり」「適当な返事をする」。聞こえる人間からしたら、どうしてきちんと聞き返したり、確認したりして、責任のある態度をとらないのと思うかもしれませんが、聞こえる社会の中で生きていく難聴者が、すべてきちんと聞き取り、確実に理解し行動していくのは至難のわざ。自らを守るために身につけたこうした処世術を一概に非難はできない。わが子にも小さいときはきちんとわかりなさい、何度でも聞き直しなさいと言ってきたが、今はそうとばかりは言えないと思っています。難聴者のそうせざるを得なかった今までの生活や教育環境を考えるべきではないかと思います。
<これからの軽・中度の子どもたちはどうであってほしいか>
最後に、これからの軽中度の子どもたちはどうであってほしいかを、お話します。これは思春期の真っただ中でいろいろな悩みを抱えているわが子に対して思うことでもあります。
聞こえない世界を、もっとよく知ってほしい(親は今まで聞こえる世界をわが子に伝えてばかりいました。もちろん聞こえる世界を伝える役目も大事ですが、聞こえない世界を伝える道筋もどこかでつけておくべきだと思います)
そして、聞こえる世界と聞こえない世界の両方を知る者として、それを誇りにしてほしい。そうした誇りを持てるような教育をしてほしいと思います。
それに関してある高校男子生徒の『俺の場合』という主張を紹介します。
『俺の場合』
「俺くらいの聴力の人は(良耳聴力90dB)、聞こえない事を表現するのには限界があり、話を全て理解するのにも限界があると思う。俺の聴力は比較的軽い方です。発音もきれいと言われます。1体1でなら、声を聞き、話すこともできるけど、集団の中ではそれができない。しかし、聴力が軽いために、他の健聴の人は、俺が聞こえると勘違いする。その勘違いを正すためにいろいろなことをやりました。「俺は聞こえない」と言っても、1対1で話せるのだから、と信じてもらえない。筆談を頼んでも、「聞こえるんだから」と取り合ってもらえない。
中学生の時に全校生徒の前でその事について作文を書いて発表したけど、「軽いくせに大げさなこと、言わないで」って言われたまま効果なかった。要するに、俺は、聞こえる、聞こえないと二つにわけた時、自分はそのどちらでもない、はざまの位置に立たされているんだな、と思った。
そのことを、日系アメリカ人に例えると分かりやすいかもしれないと思う。誰かに「どちらが、あなたにとって母国か」と尋ねられたら、きっと戸惑うはずです。それと同じように、俺は、誰かから、「聞こえないのか、聞こえるのか、どっちなんだ」と聞かれたら、答えられません。
しかし、こういう人もいるでしょう。「割り切っちゃえば、いいじゃん。」俺が考えるに、割り切るということは、“聞こえるか、聞こえないか、どちらかをはっきりさせる”という事でなく、双方のどちらかに偏ってしまう事だ、と思うんです。もしも、自分は聞こえると言い張る人がいたら、それは情報を求める事を半ば諦めてしまっている人ではないでしょうか。
俺は、そういう立場の人は、中途半端だと思うから、割り切りたくないんです。はっきりと、自分は中立している人間だと、自覚をもって生活したいんです。」
このようなことを考えている高校生をうまく伸ばしていってくれる教育の場があるといいなと思っています。これからは新生児聴覚スクリーニングなどで早期に発見される軽中度のお子さんも、福祉的な支えが得られるようになってほしいと思います。軽度だとはいえ補聴器が必要な子には、教育的見地からなんらかの補助がほしいです。また手話を親子で学ぶ場も必要だと思います。子どもを早く手話に触れさせたいと思っても、手話講習会では子ども連れは断られてしまいます。
教育の場にも一人一人の力を十分に伸ばせるように十分な体制がほしい。ろう学校で学びたいと思う中等度の子がいたら、その子のいろいろな力を十分に伸ばしてあげられる教育であってほしいです。人格形成の上で、あまりにも負の面を負いすぎないように、それでいて学習面でもきちんと保障されること、そのような教育の場を軽・中度の子どもたちにぜひぜひ用意してほしいと願っています。
以上、話があちこちに行きましたが、最後まで聞いていただき、ありがとうございました。